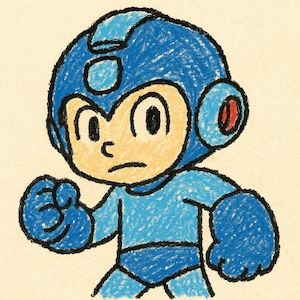いまやオタクや推し活文化のファン活動はあちこちで当たり前に盛り上がってるわけですがそんな中で「企業とファンの距離感」って意外とセンシティブな話題ですよね。
これまでのカプコンは暗黙の了解でファン活動をうまく黙認してくれてた印象がありました。ありがたいやつ。でも今回の発表を読むと「うちはこういうラインで考えてます」っていう立場をはっきり出してきた。つまり明文化です。
どうも背景にはグローバル展開とかブランドイメージの安定とかそういう企業的事情も見え隠れしてて。だからといっていきなり締めつけるわけじゃなくて「ここまでならOK」「ここから先はNGです」っていうちょっとした区切り線を引いた感じです。
筆者としてはこれはかなり大きな意味を持つ流れだと思っています。
なぜかというと推しの現場は「自由な創作の温床」みたいな空気がずっと根っこにある場所で同人やコスプレ、フィギュアの自作活動が本気で盛んなエリアじゃないですか。そういう場において「企業のガイドラインが明確になった」ということは、活動の安全圏や注意すべきこともぐっとリアルに見えてきたという事です。
そこで今回はこの切り口で考察してみました。
「カプコンの二次創作ガイドラインは創作文化圏のクリエイターにとってどう作用するのか?」
この記事ではその問いに対して、
・ガイドラインで実際に書かれてること
・それをどう受け止めるべきか
・ファン活動をする側が、どこを気にしたらいいのか
・そして秋葉原カルチャー全体にとって何が言えるのか
このへんを筆者なりにまとめていきます。
難しく考えるよりもこれを読んで「なるほどこう動けばいいんだな」って思えるような整理を目指して書いていきますね。秋葉原で創作を続けていきたい人はぜひ最後まで読んでみてください。
カプコンがついに明文化!「二次創作ガイドライン」ってどんな内容?
では、ここからはカプコンが2025年11月4日に公式発表した「二次創作ガイドライン」の中身をなりに分かりやすく整理していきます。
これ、難しく見えるけど創作活動してる人にはめとても実用的な内容なのでしっかり押さえておきたいところです。
どこまでが「二次創作」なのか?
まずカプコンの定義から。
カプコンが権利を持ってる著作物、つまりキャラクターやストーリー、音楽にビジュアル素材……そういったものを元にしてファンが自分なりの創作を加えた作品のことを同社は「二次創作」と呼んでます。
対象になるのは以下のようなもの:
・イラスト
・マンガ
・小説
・立体作品(フィギュアやガレキ)
・音楽アレンジ
・コスプレ衣装
・写真・動画など
ちなみに動画に関しては別途「動画ガイドライン」が適用されるからそっちはそっちでチェックが必要。
対象外になるのは、
・他社作品とのクロスオーバー
・実在人物の肖像使用
・カプコンロゴやタイトルロゴの流用
・ゲーム素材を直接切り貼りする使い方
つまり「自分の創作性」がちゃんと入ってるかどうかが大事ってことですね。
クレジット表記のこと
これは意外と見落としがちなやつ。
作品を公開する際には「これは二次創作ですよ」とか「カプコンのIPを使っています」といった明記をなるべく入れてくださいってガイドラインで呼びかけられてます。
ただし「書いてなかった=即削除」みたいなことにはならないとも書いてある。なので努力目標レベルとはいえちゃんと書いておいた方が安心。
一方で「©CAPCOM」って表記を自作に入れちゃうのはNGです。これは公式作品と誤解されちゃうから。
お金を取っていいのか問題
これ多くの人が気になってるポイント。
ガイドラインでは「原則として営利目的はNG」とされています。
とはいえ例外的に「趣味の範囲」で少部数を有償頒布することは容認されている、とのこと。ここで言う趣味の範囲というのは、たとえばコミケや同人誌即売会での販売と考えられます。
ただし「どこまでが趣味の範囲か」の線引きはカプコンが判断するというスタイルで明確な基準は示されてません。
つまり「明らかに商売っ気強すぎるのはアウト」という感覚的な理解が必要。
あと、立体作品ーつまりフィギュアやガレージキットの販売に関してはワンフェスなどの版権申請済イベントでしか認められていません。これは従来通りのルールです。
誰が対象? 法人は別扱い
このガイドラインが適用されるのは個人または法人格のない団体(=同人サークル)です。
法人格を持つ会社・団体が二次創作をする場合は別途カプコンのライセンス窓口とやり取りする必要があります。
つまり、法人で二次創作Tシャツを作って販売するとかそういう動きはライセンス交渉必須です。こっそりやるのは危ないのでやめましょう。
NG項目(禁止されてること)
いわゆる「これはアウトです」一覧。
- 営利目的(※趣味の範囲を超えるもの)
- 差別・ヘイト・わいせつ・反社会的・誹謗中傷など
- 宗教・政治・思想プロパガンダの使用
- 他人の権利を侵害しているもの
- 素材をそのまま使っただけの模写・切り貼り
- 作品・キャラのイメージを損なう表現
- 「公式っぽく」見せてるもの(誤認の恐れ)
- 営業妨害・模倣品・ロゴそのまま使用など
- その他「これは無理」とカプコンが判断したもの
つまり、表現の自由を守りながらも「それ、さすがにやりすぎだよね」というゾーンは明確にアウトとされています。
注意点と最後はカプコン判断の原則
ガイドラインに沿っていたとしても最終的にはカプコンの判断で「これはやめてください」と言われることがあります。その場合、制作者側が被る損害についてカプコンは責任を持たないというスタンスです。
また、ガイドライン自体も事前告知なしで変更される可能性があると明記されています。
ですので「今OKでも来年はNGになってるかも」というリスクは常にあるということです。
あと「○○って使っても大丈夫ですか?」という個別の問い合わせには一切答えませんという点も記載されています。要するに自己判断と自己責任が求められる世界観ですね。
筆者が読み解く発表の狙い
ここからは前章で整理した「カプコン二次創作ガイドライン」の中身を踏まえて筆者なりに仮説を検証していきます。読み解く軸は2つ。
ひとつはクリエイター/ファン視点もうひとつは秋葉原を中心とした推し活文化圏としての現場感覚です。
明文化は排除ではなく共存の意思表示
まず注目したいのはカプコンが「創作にあたって個別連絡は不要」とはっきり明言している点です。
筆者の知る限り、こうしたスタンスを明文化するゲームメーカーはまだ少数派です。むしろ「黙認のままグレーな関係で放置」という対応がこれまでの業界の基本線でした。
今回のようにガイドラインという形で明文化したうえで同人誌即売会などの活動を趣味の範囲として肯定的に捉えているのはファン文化を排除するどころか共存を前提にした関係を築こうとしている姿勢と受け取ることができます。
ファンにとってもクリエイターにとっても「何をしたらNGなのか」がある程度見える状態は安心材料になるはずです。
「営利」の線引き
とはいえ現場に立つクリエイターとして見逃せないのが営利と趣味の境界があいまいなまま据え置かれている点です。
「少量・少額ならOK」という一文は確かにありますがその定義について具体的な数字や部数や価格帯は一切示されていません。そして「それが趣味の範囲かどうかは当社が判断する」とも明記されています。
たとえば、同人誌を頒布するときに予想以上に人気が出て増刷した→予想より原価が高くなって頒布価格を上げた。そんなちょっとした判断でも営利目的と解釈されてしまうリスクは否定できません。
この点についてはこのガイドラインの創作者側に大きな自己判断を強いる部分だと感じました。
しかしカプコン側の個々のケース全ての明示は出来ない事情も汲まなければなりません。
ここまでしてくれた企業はないのですから。
成人表現に対する制限とブランドイメージの境界
もうひとつ大きなポイントは成人向け・R18作品に対する扱いです。
禁止項目の中に「卑猥な内容」「公序良俗に反する表現」と明記されていることから、いわゆるR18ジャンルでの二次創作にはこれまで以上に慎重な表現配慮が求められます。
カプコン作品にはホラー・グロ・バイオレンスといったジャンル的に過激な描写を含むタイトルも多くそれをモチーフにした二次創作も少なくありません。けれど、一次作品の表現の強さと二次創作における表現の自由はまったく別の軸だというのが今回の運用スタンスです。
特にR18同人誌やアダルト系グッズを制作しているクリエイターは「あくまでカプコンの世界観とブランドイメージを損なわないか?」という視点で企画段階からのセルフチェックが求められるでしょう。
「公式と誤認されない」ことが活動の自由を守る鍵
ガイドラインでは「©CAPCOM」の表記禁止や「これは二次創作です」といった明記の推奨がなされています。
一方で「明記がなかっただけで削除することはしない」とも書かれており、このあたりの柔軟なスタンスは注目です。
つまり重要なのは、ファンの創作物が公式作品っぽく見えないようにするという点。これさえ配慮されていれば一定の自由度は担保される。そんな空気が読み取れます。
誤認されなければOK。クリエイターが自分の創作ですと堂々と示すことで、公式とのバランスも保たれる。これは逆に「自主表示を徹底すればかなり自由に動ける」とも解釈できるポイントです。
創作という現場で何が起こるのか
秋葉原で活動する人にとってこのガイドラインはどう響くのか。筆者の視点からいくつかのシーンでの影響するであろう予測をまとめてみます。
● イラスト・マンガ・同人誌即売会
趣味の範囲=OK という立場が明文化されたことにより「少部数・小規模・対面頒布」ならば基本的には活動可能という安心感が得られました。明確な許可ではなくてもやっていい範囲がはっきり示された意味は大きいです。
● ガレージキット・フィギュア制作
有償頒布はあくまで「版権申請イベント限定」。つまり秋葉原界隈で開催される即売イベントでもワンフェスのような当日版権がない限り販売不可ということ。これはイベント運営側にとっても対応が問われるポイントです。
● 成人向け即売会/アダルト系作品
「卑猥な内容」「公序良俗違反」の禁止条項がある以上、成人向け作品はリスクを伴います。秋葉原の地下イベントやアダルトショップでも企画段階で作品の色合いと内容を再点検する必要があります。
● コスプレ衣装・写真・動画の公開
「ロゴ使用」「公式素材の転用」「第三者との混在」がNGという条件から、SNSでのコスプレ投稿も油断できません。写真や映像の背景や衣装の構成まで含めた表現全体にガイドラインの意識を持つことが求められます。
● 秋葉原の物販・小売・POP使用
個人ではなく法人や商業店舗がカプコンIPを使ってPOPを出したり、宣伝を行う場合はこのガイドラインではなく「ライセンス申請対象」扱いになります。秋葉原の路面店やイベントブースでもキャラ使用がある場合は要注意です。
こうした観点から見ても今回のガイドラインは単に「規制するためのルール」ではなく、クリエイターと企業が共存していくための“整理とガイドだと筆者は受け止めています。
やるべきことははっきりしています。
・誤認されない形で創作を続ける
・無断転載や素材流用はしない
・あくまで自分の創作として責任を持つ
・明らかにブランドイメージを壊す表現は避ける
その基本さえ守れば、創作文化はこれからも息を吹き続けるはずです。
↓ペルソナシリーズも深く考察しています↓
ペルソナシリーズはつながっている?時系列と設定から公式情報から考察
くまおの視点👀
カプコン社が提示した二次創作ガイドラインは活動する創作関係者にとって、非常に重要な動きだと筆者は受け止めています。これまで黙認によって成立していたファン活動に対し企業側が初めて明文化という形で基準を示したことには大きな意味があります。
筆者はこのガイドラインを創作を制限するものではなく、創作を継続するための整理された枠組みとして捉えています。作品を発表する側にとってどの範囲が許容されているのかが見えることは、文化の健全な発展にとっても重要なことです。
All Write:くまお
▼ イベントカレンダー ▼